共働きの現役保育士です。
1歳児で6人につき保育士1人、3歳児で20人につき保育士1人と、大勢の子どもたちを集団で保育する保育園の先生達。
保育園の先生たちは保育に関する技術を磨くために日々努力しています。
一方、それだけの数の子どもたちを一手に引き受けられるのは、保育園生活では明確なスケジュールがあるためです。
筆者が勤務する園児80名ほどの保育園をサンプルに、保育園での1日のスケジュールと年間スケジュールを公開します。
保育園の1日のスケジュール
0歳児クラスから5歳児クラスまで、活動内容は様々ですが、共通しているスケジュールは次のとおりです。
- 7:00 登園
視診、検温
異年齢の合同保育 - 8:00 トイレ
1歳から3歳くらいのトイトレ中の子が多いクラスは、トイレの時間が決まっていることが多い。 - 8:50 合同保育終了
おもちゃ片付け - 9:00 各クラスに移動
手洗い - 9:05 朝の会
今日の予定など先生の話を聞く→朝の歌→朝のごあいさつ→季節の歌→出欠 - 9:10 0歳から2歳児クラス朝おやつ
おやつの歌→いただきます - 9:20 主活動準備
トイレ、帽子を被るなど - 9:30 主活動
お散歩・制作・室内あそびなど、天候や欠席者の状況に応じて活動内容が変わる。 - 10:40 かたづけ
- 10:45 トイレ・着替え
- 11:10 給食準備
配膳、消毒 - 11:15 いただきます
給食の歌→いただきますの挨拶→食事 - 11:40 ごちそうさま
「おかわりは長い針7まで(11:35まで)ね」など予め終わりの時間を予告してからいただきますをする場合も多い。 - 11:45 トイレ
- 11:50 本読み
午睡に入る前に読み聞かせ。おやすみのご挨拶 - 12:00 午睡
トイレが近い子などは途中で起こしトイレを促すことも。 - 14:45 目覚め
布団片付け - 15:00 トイレ、検温、手洗い
- 15:20 おやつ
- 15:45 帰りの会
今日やったことなど振り返り→サヨナラの歌→ご挨拶→カバンをしまう - 15:55 トイレ
- 16:00 順次降園、合同保育
- 18:00 延長保育
補食を食べる
概ねこのようなスケジュールで保育園生活が流れていきます。
保育園での1日のスケジュールについて、年齢別に更に詳しく解説していますので、次の記事を合わせて参考にしてください。
保育園生活ではルーティーン化した活動が多い
概ねこのようなスケジュールで保育園生活が流れていきます。
行事等の都合で、スケジュールが多少変更になることがあったとしても、朝の会・おやつ・給食・午睡・帰りの会といったルーティーン化している活動が大きく変更することはありません。
また、意外と認識されていないのが、保育園生活では活動ひとつひとつに明確な手順が決まっていることです。
保育園生活では、例えばトイレに行くという活動ひとつ取っても、きっちりと手順が決まっています。
- 上履きを自分のロッカーの前に脱ぐ
- トイレの入口に並ぶ
- トイレ用スリッパを履く
- 用を足す
- スリッパを脱ぐ
- 教室に戻り上履きを履く
- トイレが終わった子は壁際に体育座りで座る
このような動作を進級後4月から6月くらいで覚えて、毎日繰り返しているからこそ、保育園の園児たちは集団で動ける&少ない保育士で大勢の子どもをまとめられるのです。
保育園の年間スケジュール
保育園で行う行事や年間スケジュールは、保育園によって異なります。
年間行事
4月:入園式・進級式
5月:子どもの日、母の日、保育参観
6月:父の日、お別れ遠足(年長)
7月:七夕、プール開き、お泊り保育、夏祭り
9月:遠足
10月:運動会、ハローウィン、おいもほり
11月:七五三
12月:クリスマス会
1月:お餅つき、お正月お楽しみ会
2月:豆まき、生活発表会
3月:ひなまつり、卒園式
毎月1回定期的に行う行事
毎月行う行事:お誕生日会、身体測定、避難訓練
保育園ごとに異なる行事
筆者の保育園では上記のうち、お泊り保育とお餅つきは行っていません。
その代わりに、保育参観が年間1回ではなく、秋にも給食の試食会も兼ねた参観会が行われていますよ。
行事は保育園によって内容が全く異なります。保護者参加型の行事もありますが、数は保育園によって違います。
年間行事については、入園説明会などで入園前に確認することをおすすめしますよ。


まとめ
保育園のスケジュールについて紹介しました。
職員数や園児数によってもスケジュールは異なるため、利用中の保育園の先生に詳しく聞いてみるのもおすすめです。
快く教えてくれるはずですよ。
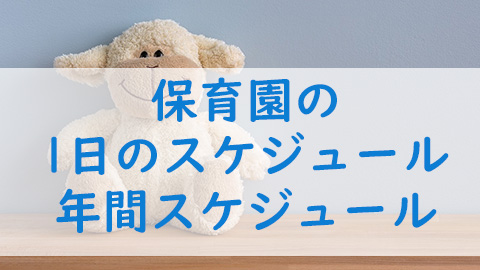






関連記事をチェックする